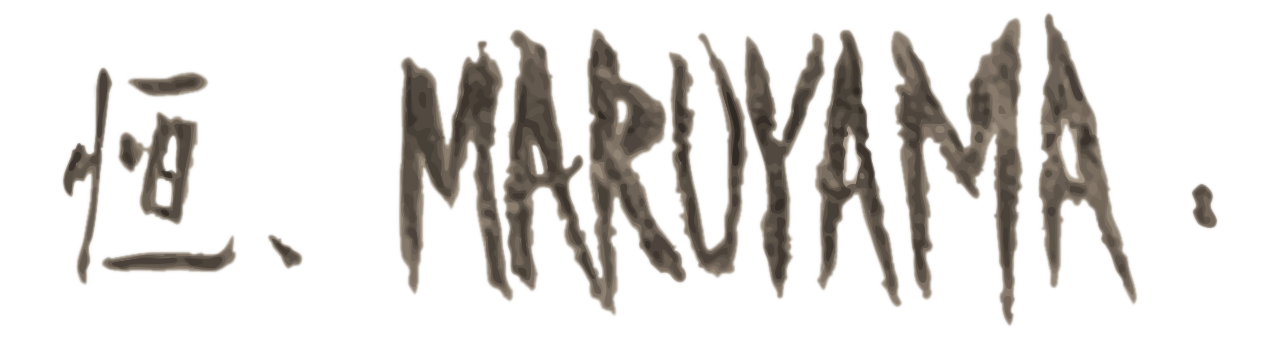Language:
鹿苑会
(「上田クロニクル ー上田・小県洋画史100年の系譜ー」より)
4 戦後の上小地域に文化の種を 岡鹿之助と鹿苑会(一部)
赤松新(半竹)や中西義男、若林市朗らはノア会が自然消滅した後、昭和15年(1940)に上田美芸俱楽部を設立。地域の画家たちの交流の場となった。この美芸倶楽部を主催した中西義男の上田市新田大輪寺前の住居には、山上喬、丸山恒雄、土屋義郎、田中康夫といった後に鹿苑会を経て春陽会で活躍した若者が出入りしていた。この若者たちのために洋画教育を施し、上小地域に文化の種を蒔こうと中西や赤松は戦後間もなく春陽会の重鎮であった小杉放菴を上田に招請し、絵画講習会を開催した。講習会の参加者の証言や記録からは日本画の指導やデッサンの指導が行われていたという。中学校の校舎で行われた講習会に、小杉放菴は広袖に下駄という風貌で現れ、一言も喋らず、ただただ若い画家たちの制作の様子を眺めていたという。
翌年も同様の講習会が開かれたが、放菴は同じく春陽会の会員の岡鹿之助に上田市に行くことを要請した。以降岡鹿之助による講評会と実技指導が昭和53年(1978)に岡が没するまで30年間行われた。その岡鹿之助の来訪を影で支えたのもノア会に参加していた中西や赤松らであった。手紙と電報でしか通信手段がなかった当時、講習会一つの調整にしても、講習会の日時、汽車や宿の手配等、様々な苦労があったことは想像に固くない。倉田白羊らと活動を共にし、大きな戦争を経た後も上田の地に美術に対する人間の息遣いを残した彼らの働きは非常に大きく、同様に美術運動の推進者として評価されるべきではないだろうか。
岡鹿之助を講師として招いた講習会は岡鹿之助の「鹿」の字をとり鹿苑会と称された。第一回は昭和23年(1948)に開催された。各々が持ってきた作品の講評、デッサンの実技指導が主な指導内容であったという。田中康夫は当時のデッサン実技指導を下記のように振り返った。「先生が僕のデッサンのところで一本線をシュッと入れてくださったんですね。そうしたら絵が決まっちゃったんですね。」裸婦像の足の描き方について苦慮していたところ、岡鹿之助がその絵に1本の線を入れただけで画面が活き、絵全体の印象が決まったという。実技指導については具体的な話はあまり得られなかったが、鹿苑会参加者が口を揃えて言うのが作品の講評の厳しさである。良い作品に出会った時は机をバンバン叩いてその感動を表現し、逆に悪い作品については言菓すくなに突き放すような言動をされ、自身も納得のいかない作品を講評に出した際には、「君はもうわかっているね」と一言告げられ、作品を返されたと厳しい面持ちで振り返ったのは現在春陽会の古参作家である浦野吉人。他会員も岡鹿之助の厳しさや講評会へ臨む際の緊張感について会報誌等様々なところで述べている。
しかし、これらの厳しさに熱い情熱を持って応えていくのが鹿苑会である。昭和39年(1964)に開催された春陽会地方講習会について当時の様子を同会会員市川治は下記のように振り返っている。「前座の学生たち数名の講評が終わると10年前と少しも変わらぬ、あのサックリとした名調子の批評が、次々に並べられる仲間たちの大量の力作に向かってパシッ”と極め、フワッと包みギリギリとえぐり出すように、時には細部にわたって始められました。8月11日早朝より夕刻まで、春陽会洋画研究会が岡先生を迎えて、信州の春陽展出品者とその又仲間達30数名が集まって開かれました。数年ぶりに先生を再び上田の地に迎えるということで、喜んで勇んで南の果て、北の辺境から仲間の作家たちがとんできました。松本地区からは柳沢先輩、小穴君、岸田たちが、飯山からは小型トラックで100号,50号を満載して、駒村君、ヒーローの浦野君、北澤君たちが、地元上田からは山上、丸山、滝ノ人、若い春原敏行達、赤松先生亡き後、上田鹿苑会の会長の仕事を引き継いで、この研究会にも一役買っていただいた若林先輩をはじめその数200点余り。」
この広い長野県内各地から山本鼎記念館に持ち寄り講評を受けるという光景は非常に熱を帯びたものであると感じられる。そして岡鹿之助は彼らの熱意に対し、鹿苑会員一人一人をプロフェッショナルの作家として向き合っていたという。
「皆さんはもう一人前(?)の作家なんですから、今日は一つお互い同士、思いきり叩き合いをしましょうよ。」「この作家の絵について、それでは〇〇君の意見を聞かせてもらいましょう。」と先生の提案で、初回から数えて十何年、今度ほど活発な意見の戦わされたのは初めてでした。と振り返るのは市川治。また、浦野吉人は「あなたたちはアマチェアではない、作家である。作家としての魂を持ちなさい。」という岡鹿之助の言葉が脳裏に強く残っているという。アマではないプロとして、言い換えれば岡と同じ土俵に作家を引き上げ、そこで対等に向き合う態度に鹿苑会の作家たちは感化されていったのではないだろうか。1950年代後半に入ると香掛利通が春陽会会員に推挙され、以降鹿苑会の作家は続々と春陽展において入選、受賞を重ね、田中康夫、丸山恒雄、池田輝、浦野吉人と多くの作家を会員として輩出していった。岡鹿之助没後3年の昭和55年(1980)に鹿苑会は解散するが、同会参加者のほとんどが後身の春陽会東北信研究会に所属。春陽会本体から講師を招いた講評会や勉強会は今日まで続いている。
鹿苑会には昭和46年(1971)に春陽会会員になった丸山恒雄のように、在野団体である春陽会や鹿苑会にこだわり、出展を春陽会一本に絞っていた作家と岡鹿之助と共に春陽会長野講習会に講師として来信し、県展にも積極的な関割を持った藤井令太郎の指導を仰ぎ新たな発表や評価の機会を得ようとする作家がいた。藤井令太郎を顧問とし、柳沢健、山上喬、市川治、丸山恒雄らが主要会員となった春陽会長野県支部が昭和36年(1961)に発足すると1年に1~2回、藤井令太郎を講師に迎えた地方講習会が調催されるようになった。岡鹿之助に強く師事していた作家は藤井の指導を受けつつも、「春陽会にこだわる」その空気感を鹿苑会の中に漂わせていたが、昭和40年(1965)より信州美術会副会長、さらには会長を歴任した藤井令太郎の存在感が強くなるにつれ、発表の自由を求める気風が鹿苑会の中に共有され始めた。県展へ出品する者や信州美術会の地方部会である上小美術会(現東信美術会)に関わる作家が増え、上小美術会においては鹿苑会から中西静男、山岸信一、沓掛利道、山崎羊ーらが会長職を歴任した。また、鹿苑会に参加した米津福祐は藤井の指導を受けながら二紀会に参加し要職を歴任。一方地域においては上小美術会会長、信州美術会副会長を経て、現在は信州美術会会長として長野県の美術シーンをリードしている。このことから鹿苑会が地域の美術活動の発展に大きく寄与していることは明らかであり、山本鼎が蒔いた種は100年にわたり多くの作家の手により育てられ、この上田地域に美術の花を咲かせてきたと言えよう。
小笠原正、日向大季「上田クロニクル ー上田・小県洋画史100年の系譜ー」小笠原正、大塚菜々美、日向大季『上田クロニクル ー上田・小県洋画史100年の系譜ー』